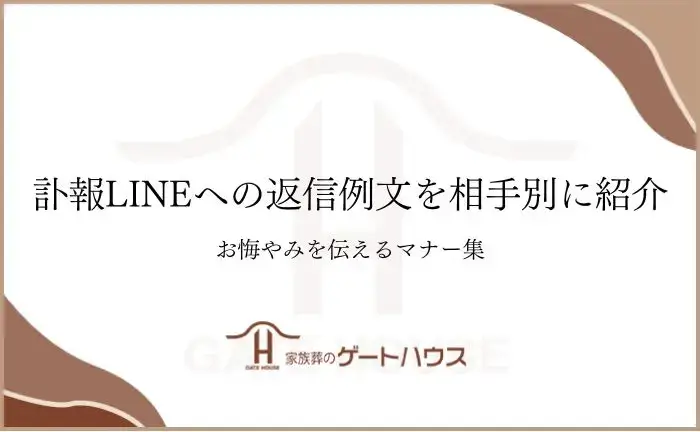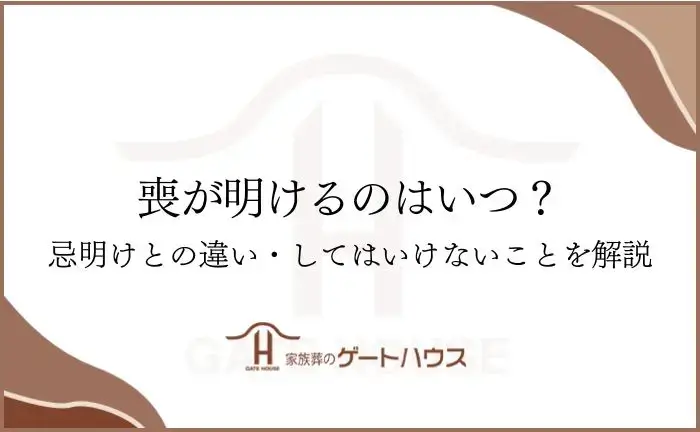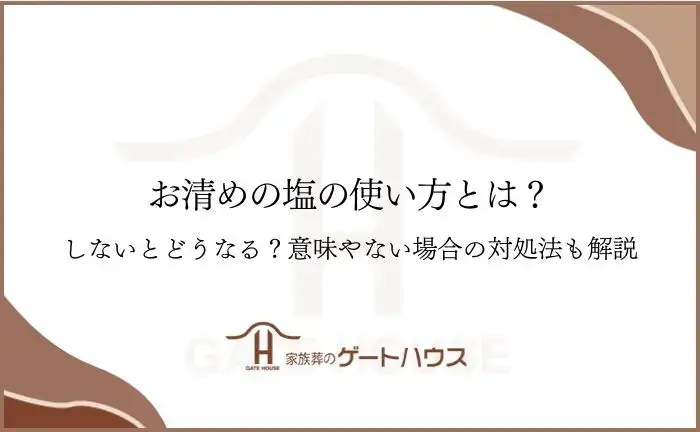浄土真宗の初盆の迎え方は?お布施相場やお供え物・仏壇の飾り方など解説
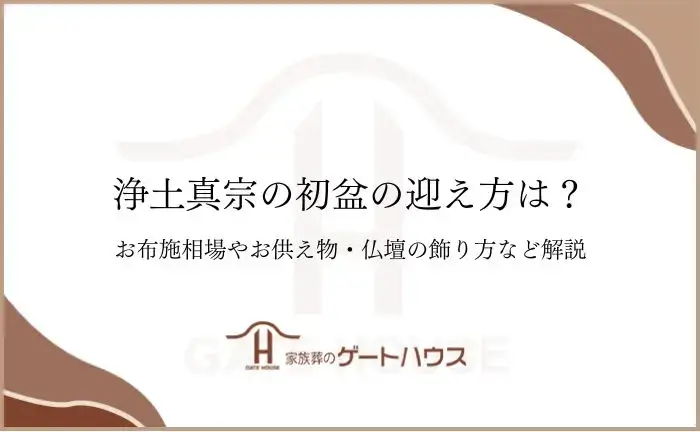
「浄土真宗ではお盆をやらない」と耳にしたことがある方もいるかもしれません。
実際、浄土真宗の初盆は、他宗派とは考え方・風習において異なる点がいくつもあります。
本記事では、浄土真宗の初盆について、他宗派との違いや準備の仕方、お布施の相場などをご紹介します。
浄土真宗の初盆は追善供養を行わない
日本では、お盆にご先祖様の霊をお迎えし、感謝の気持ちを込めて供養する仏教行事として広く親しまれています。
しかし、浄土真宗ではお盆にご先祖様が帰ってくるという考えはありません。
初盆であったとしても、お盆の追善供養は一般的には行わないのが基本です。
では、浄土真宗と他の宗派ではどういった考えの違いがあるのか詳しく見ていきましょう。
【関連記事】
新盆(初盆)とは?やり方は?用意するものやいつ法要を行うか解説
浄土真宗でやってはいけないこと16個|お通夜や葬儀・お盆など状況別に解説
浄土真宗の死生観
浄土真宗の場合、亡くなった人は阿弥陀仏の力によってこの世の苦しみから離れ、極楽浄土に往生し、仏になると考えており、これを「往生即成仏」と言います。
阿弥陀仏を信じることで故人が輪廻転生の「六道」の苦しみから救済されるという考えなので、成仏の概念が他の宗派と異なるのです。
死とは終わりではなく、新しい始まりであり、阿弥陀仏の教えや迷いのない世界の浄土で仏となられたことを喜び感謝する姿勢を重視するのが法会(法事)とされています。
※六道:仏教の教えで、人々が輪廻転生する世界(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天上道)のこと
他宗派との死生観の違い
浄土真宗以外の宗派では、死後すぐには成仏せず、故人の魂は四十九日を経て成仏に向かうとされています。
人間や動物などさまざまな存在へと生まれ変わり、死と生を繰り返すという輪廻転生の考えが一般的です。
家族や親戚などが供養を重ねることで、輪廻の苦しみから解脱し、故人の魂が安らかに極楽へと導かれるという考えがあります。
そのため、初盆(新盆)や年忌法要といった追善供養は重要な供養の機会とされています。
【関連記事】
浄土真宗の葬儀の流れは?お布施の相場や本願寺派・大谷派別に葬式の順序を解説
浄土真宗のお盆は「歓喜会(かんぎえ)」という
浄土真宗ではお盆のことを「歓喜会(かんぎえ)」と呼びます。
歓喜会はご先祖様や阿弥陀仏に感謝し、仏様の教えとの出会いや往生できることを喜ぶ日です。
供養よりも、法話会への参加やお仏壇のお参りを通じて、仏の教えに触れる機会として位置づけられています。
お盆の時期は地域によって異なり、8月13日〜16日が多いですが、関東の一部地域などでは7月13日〜16日とされているところもあります。
他宗派とのお盆の違い
多くの宗派でお盆は、ご先祖様・その他の霊がこの世に戻ってくるとされるため、地域によっては新盆法要が盛大に営まれ、お盆用品も多岐にわたって準備されます。
お盆は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」が正式な呼び方で、お釈迦様の弟子が餓鬼道に落ちた母親を救った言い伝えにちなんで、ご先祖様の追善供養を行うのが一般的です。
それにならって、今では盆棚(精霊棚)・供物を用意して迎え火を焚き、盆提灯を灯して霊を迎えます。
盆期間中は手厚く供養し、送り火によってまたあの世へお送りするのです。
一方、浄土真宗では霊が戻ってくるという考えがないため、送り火・迎え火、精霊馬、霊具膳などは必要ないとされています。
ただし、地域や親族の慣習として一部取り入れられることもあります。
【関連記事】
盂蘭盆会(うらぼんえ)とは?意味やお盆・施餓鬼会との違いを解説
真言宗の初盆飾りとは?準備するお供え物や行うこと・服装マナーを解説
曹洞宗の初盆飾りの仕方は?精霊棚(祭壇)の飾り方・お供え物・提灯について解説
浄土真宗でも初盆にお墓参りはする?
浄土真宗でも、お盆時期のお墓参りや墓石のお掃除は同じように行います。
しかしお寺に行った際は、本堂にある本尊の阿弥陀仏に先にお参りするのが一般的です。
他の宗派のように追善供養の考えはありませんので、供養のためではなく「ご先祖様を縁として阿弥陀仏を拝むこと」を目的としてお墓参りを行います。
また、故人は既に仏となり浄土にいるので、お墓に故人の魂は宿っておらず、あくまでもお墓は遺骨を納めている場所という考えです。
浄土真宗における初盆の仏壇・お供え物の飾り方
【浄土真宗 初盆の仏壇に飾るもの】
-
- 打敷
- 供笥
- 花瓶(お花)
- ろうそく
- 香炉(お線香)
- お仏飯(ご飯)
浄土真宗では、他の宗派と同様にお仏壇のお掃除はしますが、お盆飾りや盛大なお供えは基本的には不要です。
ただし、お仏壇に特別な布を飾ったり、白い丸餅をお供えしたりなど、浄土真宗独自のお飾り・お供えも存在します。
お供えや飾りに関しては、地域の風習にも合わせることもあります。
浄土真宗独自の飾りやお供えに関して詳しくみていきましょう。
打敷を敷く
具足と呼ばれる花立・香炉・火立(ロウソク立て)が置かれている前卓(まえじょく)に、打敷(うちしき)と呼ばれる布を敷きます。
打敷は荘厳具(そうごんぐ)と呼ばれる、仏壇をより華やかに飾る仏具の一つで、平常時には飾らず、お盆や法要などの特別な日に使用します。
浄土真宗で使用する打敷は三角形で、お盆には夏用に作られた白・金・青などの薄手の物を使用します。
供笥(くげ)に餅を供える
供笥(くげ)とはお供え物を載せる台で、本願寺派では六角形、大谷派では八角形のものを使用します。
これに、高位のお供え物とされているお餅(丸餅)を、鏡餅のように重ねて乗せお供えします。
お菓子や果物などを一緒に供えることもあるようです。
花瓶(かひん)に花を供える
浄土真宗では、お花は仏様への感謝の気持ちを表すとともに「仏様の慈悲の心」を分けていただくという意味合いがあります。
一般的にもお供えするお花は、生花が望ましいとされていますが、浄土真宗においては特に重要視されます。
お盆にお供えする花の種類に絶対的な決まりはありません。
他の宗派と同様にトゲや毒のある花は避け、なるべく長持ちするお花を選びましょう。
夏のお花やほおずきなどを入れて、お盆らしい雰囲気を出すのもおすすめです。
白い和ろうそくを準備する
ロウソクの灯は、仏様の知恵の象徴と考えられており、読経や法要の際に灯します。
可能ならば、和ろうそくを準備するのが良いでしょう。
浄土真宗の初盆では錨型(いかりがた)と呼ばれる、くびれがあり先が太く根元の方が細くなっている形の白い和ろうそくを使用します。
ろうそくの色は、本願寺派だと三回忌まで白・七回忌以降は赤、大谷派だと四十九日を過ぎたら赤(百か日法要から赤)とされており、朱色のろうそくを供えることもあります。
色に関しては、地域的な違いもあるようです。
盆提灯・切子灯籠(きりことうろう)を飾る
切子灯篭も、お仏壇周りを華やかにする荘厳具の一種です。
浄土真宗で使用する切子灯篭は、大谷派では上部に彫刻があり、紺と赤の染め分けがされています。
一方、本願寺派では上部が白一色で花飾りがついているなどの違いがあります。
また、一般的な盆提灯は、お盆に帰ってくるご先祖様の霊が迷わないように明かりを灯す意味がありますが、浄土真宗では先祖の霊を迎える意味はありません。
そのため、浄土真宗で新盆の白提灯は必要ありませんが、地域によって飾る場合もあります。
【関連記事】
新盆(初盆)の提灯は誰が買う?飾り方・選び方やいつから飾るのかを解説
浄土真宗の初盆で準備すること
一般的な仏教宗派と異なり、霊を迎えるという考え方は持たない浄土真宗ですが、ご縁ある方々とともに仏法に触れる行事として、丁寧な準備を進めることが大切です。
ここでは、歓喜会の法要を行うにあたって必要な主な準備についてご紹介します。
僧侶を手配する
まず最初に行うべき準備は、法要をお勤めいただく僧侶への依頼です。
浄土真宗では、初盆に限らず、僧侶によって読経が行われます。
歓喜会の時期は多くの家庭で法要が重なるため、依頼が集中しやすく、希望の日程での調整が難しくなることもあります。
できるだけ早めにお寺に相談し、日程と場所を確定しておきましょう。
会場を自宅以外の斎場や寺院で行う場合は、その場所の予約も併せて進めます。
【関連記事】
初盆(新盆)の服装マナーとは?男性・女性別の着こなし方や注意点を解説
参列者への連絡・会食場所を手配する
歓喜会には、親族だけでなく、生前にご縁のあった友人・知人などを招くことが一般的です。
日程と会場が決まり次第、できれば1か月前までに案内状を送りましょう。
案内状には、出欠の返信を確認できるよう往復はがきや返信用の封筒を同封するのが丁寧です。
参列者の人数がある程度確定したら、会食の準備も始めます。
法要後に会食を行う場合には、自宅で仕出し料理を用意するか、近隣の会食会場や料理店の手配を進めておきましょう。
【関連記事】
新盆を家族だけで自宅で行うには?お坊さんを呼ばないときのお布施や香典も解説
返礼品の準備をする
香典をいただいた参列者には、感謝の気持ちを込めて返礼品をお渡しするのが一般的です。
定番の品としては、お茶・お菓子やタオルセット、洗剤などの日用品がよく選ばれています。
金額の相場は1,500円〜5,000円程度が目安とされ、相手に気を使わせない程度のものがよいでしょう。
持ち帰りの負担にならないよう、かさばらないサイズ感の品を選ぶと親切です。
万が一、急な参列があった場合に備えて、人数分よりも少し多めに用意しておくと安心です。
【関連記事】
初盆(新盆)のお返しにタブーはある?品物の選び方や相場なども解説
浄土真宗の初盆のお布施相場
お布施相場はお寺によっても異なりますが、3,000円~5,000円程度が一般的とされています。
自宅に来てもらう場合は30,000円~50,000円程度が相場です。
お布施を渡す際は、水引のない白い封筒に「御布施」または「お布施」の表書きをし、お金を包んでお渡しするのがマナーです。
また、直接手渡しはせず、袱紗(ふくさ)や風呂敷に包んで持っていき、その上に乗せた状態でお渡しする形が丁寧とされています。
初盆法要として自宅に来てもらった場合は、切手盆と呼ばれる黒塗りのお盆や袱紗の上に乗せて渡します。
浄土真宗の初盆はご先祖様への感謝や祈りをささげる期間
浄土真宗では一般的なお盆でイメージする迎え火・送り火、初盆の祭壇飾りなどは行いません。
しかし、仏壇やお墓をきれいに整え、ご先祖様や仏様に想いを馳せて手を合わせて過ごすという点では、他の宗派と共通しています。
初盆であっても特別な準備は必要ありませんが、大切な方のはじめてのお盆をお迎えすることとなります。
阿弥陀如来の教えに触れる機会、気づくための期間として大切にしましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要